みなさんは「相場の大底で起きていること」を理解をされていますでしょうか?
株式市場の動きは分かっていると思っていても、予想と違う動きをすることが多いなと個人的には感じています。だからこそ経験則もとても大切だと考えていて、市場の動きを経験則からもみるようにしています。
また米国市場は特に不透明な時期にありますのでこういった経験則から市場全体を見ておくことに意味があるのではないでしょうか。この大局観についてとても参考になるコラムを2018年6月29日にSBI証券のコラムで広瀬隆雄さんが説明されていましたのでこの記事で内容をシェアさせていただこうと思います。
分かっているという方もぜひ復習の意味で最後まで読んでいただけると幸いです。

ということで今回は「【広瀬隆雄さん】相場の大底で起きやすいこと」についてです。
【この記事をみて分かること】
・もうはまだなり
・強気のわな(Bull trap)
・持ち株の処分
・弱気から無関心、そして大底へ
初心者でもとても使いやすい投資ツール
moomoo証券アプリ!
・ヒートマップで市場動向を一目で把握
・バフェットの保有銘柄もチェック可能
・豊富な分析ツールが無料で使い放題!
もうはまだなり

(もうそろそろ買い場じゃないか?)……これが「もうはまだなり」という相場の格言の「もう」の部分です。
投資家がそう考えているうちは、まだ買い場じゃないという意味だと広瀬氏は言います。
このように「下げ相場の初期には投資家は楽観的なスタンスを堅持しつづける」と広瀬氏は言います。マーケットが値幅面で大きく下がった場合、(これだけ下がったのだから、もういいだろう)と思うのは人情ですが、相場の調整には「値幅」と「日柄」という二つの要素があるとのことでした。
ちなみに「日柄」とは、つまり経過時間を指します。
相場が出直るには割安感が出るだけではダメで、ある程度の時間的休養が必要だと広瀬氏は述べていました。
また広瀬氏は三圃(さんぽ)式農業という言葉を用いて、耕地を休ませるために1) 冬穀(秋に種を蒔く小麦やライ麦など)、2) 夏穀(春に種を蒔く大麦・大豆など)、3) なにもしない休耕地、という三つに区分し、それをローテーションさせることで地力の低下を防ぐ農法だと説明をしていました。
つまり「なにもしない」ということは別にサボっているのではなくて、農地を消耗させないための知恵とのことでした。株式市場にもこれに似たことがあてはまると広瀬氏は言います。
すなわち人気化し、投資家にいじり尽くされたマーケットは栄養を消耗し切っているので、すぐに出直ろうと思ってもエネルギーの蓄積が足らないためヘナヘナと再び下落しやすいと仰っていました。
この点については投資をしている方なら分かると思いますが、ご自身が検討をしている個別銘柄やETFが株価を下げている時にここまで下がったのでエントリーしてもいいだろうと考えることはよくあるのではないでしょうか?
ではこの段階では何が起こるのか?次章で広瀬氏の言葉をまとめておきますね。
強気のわな
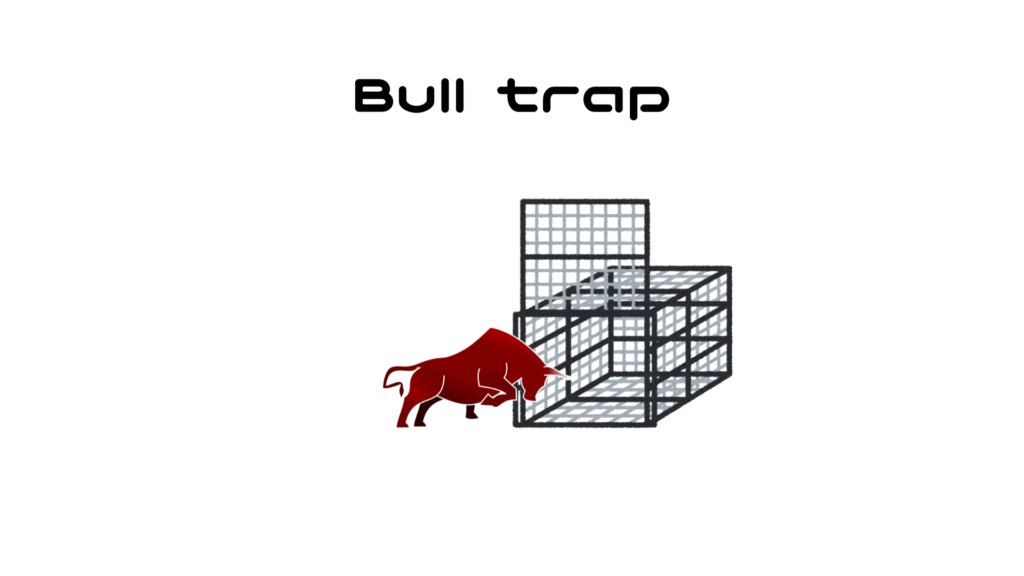
下落相場の初期には、突然、マーケットが盛り返し、「ほら、もう大丈夫!」と思わせる場面があります。
これを「強気のわな(Bull trap)」と言います。
「強気のわな」は、いわゆる「騙し」に他ならず、この「騙し」にうかつに手を出すと、またすぐに相場が下がり始め、ただでさえ弱気相場で損を抱えているのに更に傷口を大きくする結果を招くと広瀬氏は言います。
大体、ベア・マーケット(=下落相場)の初期は未だ経済指標もそれほど悪くなっていないし、ほんの数カ月前の株式市場のバリュエーションと比べると(ずいぶん安くなったな)という印象を与えるので、ついつい安易な気持ちで出動しがちになります。
この点について安易にエントリーしてしまう気持ちはとても理解ができますが注意をしておこうと思います。
また広瀬氏は投資信託や年金を運用している機関投資家は、相場を張ることによって受益者から報酬を貰っている関係で、少し相場が安くなっただけですぐ「それ買い場だ!」と出動してしまいやすいようです。つまり機関投資家はフル・インベストメントのバイアスがかかっているとのこと。
なぜなら相場の反騰局面を取り逃がすと「サボっていたのではないか?」と疑いをかけられるからだと説明をされていました。
このバイアスは私たち個人投資家にはないかと思いますが、もしこのまま上昇したら利益を享受できなくなるという焦りから購入を急いでしまうケースはあるのではないでしょうか?
また広瀬氏は「騙し」にひっかかることを繰り返すと投資家は用心深くなり(もうこれ以上、投資資金を消耗しないぞ!)と心に誓うと言います。すると市場参加者が少なくなるので自ずと出来高も閑散になるようで、つまり新規の買いは控えるけれど、一部の持ち株だけは我慢して持ち続けると説明をされていました。
この段階でも、未だ大底ではないとのこと。つまり誰も売りたくないという状況は、まだアク抜けではないからです。
この時期になると景気の先行指標である株価の下落に、ようやく実態経済が追い付き、実際に景気指標が悪くなっていることを示す経済指標が出始めるとのことで、株価が弱気相場に入ってからこのように景気指標が悪化し始めるまで1年くらいを要する場合もあるようです。
①設備稼働率の低下
②高工業生産の低迷
③自動車販売台数の下落
④住宅着工件数の低下
⑤新規質業保険申請件数の増加
⑥失業率の上昇
⑦倒産件数の増加
ちなみに具体的に景気が悪くなっていることを示す例として、広瀬氏は上記をあげています。この点は頭の片隅にでも入れておくといいのではないでしょうか。
【日本では無料公開】
最高ランク厳選米国銘柄を紹介!
1万銘柄以上の中から選ぶトップ0.1%銘柄を
50年以上の歴史がある投資格付け機関
「Weiss Ratings」が紹介!
持ち株の処分

さらに景気後退が深刻になると金融システムそのものが揺さぶられる場合もあり、中央銀行は利下げすることにより経済を刺激するとともに市場に対する流動性を供給する点に広瀬氏は触れていました。
ちなみに一般的に「金利と株価はシーソーの関係」と言われることがあります。つまり利下げをすると株価は上がり、逆に利上げをすると株価が下げる傾向があることは覚えておくといいかと思います。
また広瀬氏はこの時点で企業や個人は景気後退が濃厚となると倒産や解雇を恐れて借金を整理しなるべくキャッシュを積み上げることを考えると言っていました。さらに個人投資家の場合、株式市場と金輪際縁を切るため残っていた持ち株をバッサリ処分するとのこと。
その頃までには自分の資産は弱気相場で随分目減りしているわけだけれど、そのなけなしの持ち株すらも綺麗さっぱりサヨナラするわけです。この時点では、もう売るのを我慢している持ち株すらないので、戻り待ちの売り圧力は無いと広瀬氏は仰っていました。
では相場の大底はどのような時期にくるのか広瀬氏の言葉を次章でまとめておきますね。
弱気から無関心、そして大底へ
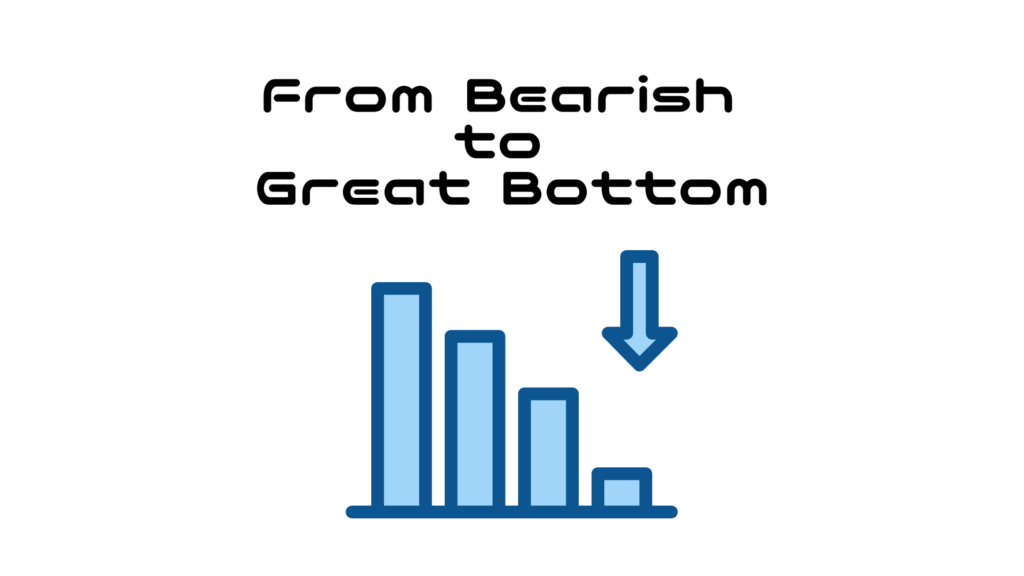
不景気が長引くと次第に投資家はリスクに対して極めて敏感になり、少しでもおカネを損する可能性のある事に対してはアレルギー的な反応を示すようになり、極端に保守的な態度になると広瀬氏は言います。
もちろん熱狂のかけらもなく、投資家は只々ちぢこまった態度を示していて、相場に乗り遅れることを心配する人は一人も居なくなると説明をされていました。それどころか一切投資から身を引く投資家も続々と出てきます。株式市場が誰からも顧みられなくなると述べていました。
そしてその頃になると株価の下落によりいつのまにか株式利回りが債券利回りを上回るようになるようで、商いは極端に細っており、メディアも株式市場の出来事を報道しないので、相場が静かに反転しても誰もそれに気が付かないとのこと。
しかし、いつの間にか新安値銘柄数は減っており、騰落線も増加に転じていき、このような時にひっそりと株価は底入れすると広瀬氏は仰っていました。
つまり「投資家およびメディアが株式市場に関心をなくしていて、新安値の銘柄がなくなった段階」で相場の大底がくると広瀬氏は言っているのではないでしょうか。ですのでよくVIX(恐怖指数)の数値やFear and Greed Indexなどで投資家心理も確認をしながら市場をよく観察をしておこうと思います。
また広瀬氏は殆どの投資家は、そもそも資金が尽きてしまっているので、相場の反転を機に参入しようという考えすら起きまないと言います。さらに経済を巡るニュースはその時点でも未だ悪いものばかりの筈だと。
つまりここでも株価には先見性があるので、まだ経済指標が悪くても、一足先に株価は底入れすると説明をされていました。
そして弱気相場は、時として3年ほど続くこともあって、弱気相場が長ければ長いほどエネルギーを蓄積しているので次の強気相場は力強いものになると締めていました。
いかがでしたでしょうか。
この内容がもちろん必ず当たる訳ではないかもしれませんが相場のサイクルを理解しておくだけでも価値はあると個人的には思います。市場の動向と投資家心理を追っておくことの重要性にあらためて考えさせられる内容だと思ったのでこのブログでもシェアさせていただきました。
この内容がみなさんの投資にとって少しでも役に立てれば幸いです。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!
【情報収集に必須な投資ツール】
投資初心者にもおすすめmoomoo証券アプリ!
ヒートマップの確認やバフェットの投資銘柄が簡単検索!
またダウンロード+入金だけで最大10万円相当の株がもらえる
~キャンペーン終了前にぜひダウンロードして下さい~
それでは今回の情報が検討される際の参考になれば幸いです。



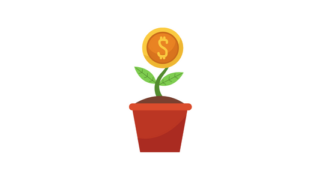





※当ブログではアフェリエイトによる広告を掲載しています※